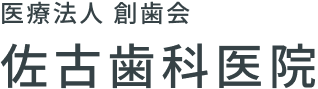2025.08.12
【歯科医師が解説】インプラントのよくあるトラブル事例と原因|すぐにできる対処法も紹介
はじめに
失った歯の機能と見た目を回復させるインプラント治療は、天然歯に近い噛み心地を取り戻せる優れた治療法として、多くの方に選ばれています。
しかし、外科手術を伴うため、「もしトラブルが起きたらどうしよう」と不安に感じる方も少なくありません。
実際に、インプラント治療にはいくつかのトラブル事例が報告されています。
しかし、その多くは原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで予防・解決できるものです。
この記事では、歯科医師の立場から、インプラント治療で起こりうるトラブルの具体的な事例とその原因、そして万が一トラブルが起きた際の対処法から、トラブルを未然に防ぐための予防策まで、詳しく解説します。
この記事を読んでいただければ、インプラント治療への漠然とした不安が解消され、安心して治療に臨むための知識が身につくはずです。
そもそもインプラント治療とは?
本題に入る前に、まずはインプラント治療がどのようなものか簡単にご説明します。
インプラント治療とは、歯を失った部分の顎の骨に人工歯根(インプラント)を埋め込み、その上に人工の歯を装着することで、機能と見た目を回復させる治療法です。
天然歯とほとんど変わらない噛み心地と美しい見た目を取り戻せるため、非常に優れた治療法ですが、外科手術を伴うからこそ、その内容とリスクを正しく理解しておくことが重要です。
治療は精密な診断から手術計画、インプラントの埋め込み、最終的な人工歯の装着という手順で進みますが、この各段階で予期せぬトラブルが発生する可能性もゼロではありません。
どのようなトラブルが起こりうるのかを事前に知ることが、後悔のない治療につながる第一歩となります。
【治療段階別】インプラントのよくあるトラブル事例
インプラントのトラブルは、治療後の時期によって発生しやすいものが異なります。
ここでは「手術直後〜数ヶ月」「数ヶ月〜数年後」「10年以上経過後」の3つの期間に分けて、代表的なトラブル事例をご紹介します。
1. 手術直後〜数ヶ月に起こりやすい初期トラブル
インプラント体を顎の骨に埋め込む手術の直後から、骨とインプラントが結合するまでの期間(2〜6ヶ月程度)に起こる可能性があるトラブルです。
▼事例①
【手術後の痛み・腫れがなかなか引かない】
手術後、2〜3日をピークに1週間程度は痛みや腫れが出ることがありますが、これは正常な治癒過程です。
しかし、1週間以上経っても強い痛みが続いたり、一度引いた腫れが再びひどくなったりする場合は注意が必要です。
◯原因
細菌感染、手術による組織の過度な損傷、インプラント体への早期の過剰な負担などが考えられます。
◯対処法
我慢せずに、すぐに手術を受けた歯科医院に連絡してください。
感染が疑われる場合は、抗生物質の投与や洗浄などの処置が必要です。
▼事例②
【出血が止まらない】
手術当日から翌日にかけて、唾液に血が混じる程度の出血は問題ありません。
しかし、口の中が血でいっぱいになるような出血が続く場合は、異常のサインです。
◯原因
縫合した傷口が開いてしまった、あるいは太い血管を傷つけてしまった可能性が考えられます。
◯対処法
清潔なガーゼなどを丸めて傷口に当て、20〜30分ほどしっかりと噛んで圧迫止血を試みてください。
それでも止まらない場合は、夜間や休日でもためらわずに歯科医院へ連絡しましょう。
▼事例③
【唇や顎に麻痺・しびれが残る】
下顎のインプラント手術で、ごく稀に起こる偶発症です。
手術後、麻酔が切れても唇や顎、舌の感覚が鈍いままだったり、ピリピリとしたしびれが残ったりする症状です。
◯原因
インプラントを埋め込む際に、顎の骨の中を通る神経(下歯槽神経など)を傷つけたり、圧迫したりすることが原因です。
◯対処法
症状に気づいたら、すぐに歯科医師に伝えましょう。
多くの場合は一時的なもので、数週間から数ヶ月で回復しますが、ビタミン剤の投与や星状神経節ブロック注射などの治療が必要になることもあります。
術前のCT撮影による精密な診断が、このトラブルを避けるために極めて重要です。
▼事例④
【インプラントが早期に抜けてしまう】
インプラント体と骨がうまく結合せず、グラグラしてきたり、自然に抜け落ちてしまったりするケースです。
◯原因
患者さんの骨質が非常に柔らかかった、骨の量が不足していた、初期固定が不十分だった、喫煙や糖尿病などにより治癒が妨げられた、といった要因が挙げられます。
◯対処法
原因を精査した上で、骨造成(骨を増やす処置)などを行い、再度インプラント手術を行うか、他の治療法(ブリッジや入れ歯)を検討することになります。
2. 数ヶ月〜数年後に起こりやすい中期的トラブル
インプラントが骨と結合し、被せ物(上部構造)を装着して食事ができるようになった後に発生するトラブルです。
▼事例⑤
【歯茎の腫れや出血(インプラント周囲炎)】
インプラントトラブルの中で最も多く見られるのが「インプラント周囲炎」です。これは、インプラントの周りの組織が歯周病菌に感染して炎症を起こす病気です。
◯症状
天然歯の歯周病と同様に、歯磨きの際の出血、歯茎の腫れや赤み、膿が出るなどの症状が現れます。進行するとインプラントを支える骨が溶かされ、最終的にはインプラントがグラグラになって抜け落ちてしまいます。
◯原因
最大の原因は、日々のセルフケア(歯磨き)不足によるプラーク(歯垢)の蓄積です。また、定期メンテナンスを怠ることも大きなリスク要因となります。
◯対処法
初期段階であれば、歯科医院での専門的なクリーニングとセルフケアの改善で回復が見込めます。進行している場合は、歯茎を切開して清掃する外科処置が必要になることもあります。
▼事例⑥
【被せ物(上部構造)の破損・脱離】
インプラント体の上に取り付けた人工の歯(被せ物)が、欠けたり、割れたり、外れたりするトラブルです。
◯原因
歯ぎしりや食いしばりによる過剰な力、非常に硬いものを噛んだ際の衝撃、経年劣化などが考えられます。
◯対処法
破損した被せ物は修理または再製作が必要です。
外れただけの場合は、そのまま再装着できることもあります。
歯ぎしりの癖がある方には、就寝時にマウスピース(ナイトガード)を装着することをお勧めします。
▼事例⑦
【インプラント体と被せ物をつなぐネジの緩み・破折】
インプラント体と被せ物は、小さなネジで連結されています。このネジが噛む力によって緩んだり、稀に折れたりすることがあります。
◯原因
噛み合わせのバランスが悪い、過度な力がかかっていることなどが原因です。
◯対処法
ネジが緩むと被せ物が少し動くように感じます。放置するとネジの破折につながるため、異常を感じたらすぐに受診してください。
定期メンテナンスでネジの緩みをチェックすることが、破折を防ぐ上で非常に重要です。
3. 10年以上経過後に起こりうる長期的トラブル
長期間にわたって問題なく機能していても、起こりうるトラブルがあります。
▼事例⑧
【インプラント体の破折】
非常に稀なケースですが、インプラント体そのものが金属疲労などで折れてしまうことがあります。
◯原因
長期間にわたる過度な噛み合わせの力、歯ぎしりなどが主な原因です。
◯対処法
破折したインプラント体を取り除き、骨の状態が良ければ再手術を検討します。
撤去が困難な場合もあります。
▼事例⑨
【加齢による口腔内の変化への不適合】
加齢とともに歯茎が下がったり(歯肉退縮)、周りの天然歯が移動したりすることで、インプラントと周囲の組織とのバランスが崩れることがあります。
◯原因
生理的な加齢現象や、残っている他の歯の歯周病などが原因です。
◯対処法
歯茎が下がりインプラント体の一部が見えてしまうと、見た目が悪くなるだけでなく、清掃も難しくなります。
定期メンテナンスで噛み合わせの調整やクリーニングを継続し、口腔内全体の健康を維持することが大切です。
インプラントトラブルの主な原因まとめ
これまで見てきた様々なトラブルは、主に以下の原因に分類できます。
① 患者さん側に起因するもの
・セルフケア不足:毎日の歯磨きが不十分でプラークが溜まっている
・定期メンテナンスの中断:歯科医院でのプロのチェックや清掃を受けていない
・喫煙:血流を悪化させ、感染リスクを高め、治癒を遅らせる
・全身疾患:コントロール不良の糖尿病などは、免疫力を低下させ感染しやすくなる
・悪習癖:歯ぎしりや食いしばりは、インプラントに過剰な負担をかける
② 歯科医院側に起因するもの
・術前検査・診断の不足:CT撮影を行わず、骨の量や神経の位置を正確に把握していない
・技術・経験不足:不適切な位置や角度にインプラントを埋入してしまう
・衛生管理の不徹底:手術時の滅菌環境が不十分で、細菌感染を引き起こす
・不適切な治療計画:噛み合わせを考慮しない被せ物を作製してしまう
トラブル発生した際に『すぐにできる対処法』と『やってはいけない』こと
もしインプラントに「グラつく」「痛い」「腫れた」などの異常を感じたら、どうすればよいのでしょうか。
すぐにやるべきこと
① すぐに歯科医院へ連絡・相談する
最も重要なことです。自己判断で様子を見るのは絶対にやめてください。
トラブルは初期段階で対処するほど、大事に至らずに済むケースがほとんどです。
「これくらいで電話していいのかな?」と遠慮せず、まずは状況を伝え、指示を仰ぎましょう。
② 患部を清潔に保つ
歯科医師の指示があるまでは、患部を指や舌で触らないようにしましょう。
食事の後は、刺激の少ないうがい薬やぬるま湯で優しく口をすすぎ、清潔を保ちます。
やってはいけないこと
① グラつくインプラントを自分で押し込む・触る
気になっても、自分で元の位置に戻そうとしたり、揺らしたりしないでください。
周囲の組織をさらに傷つけ、状態を悪化させる可能性があります。
② 硬いものや刺激物を食べる
患部に負担がかかるような食事は避け、うどんやおかゆなど、柔らかいものを食べるようにしましょう。
トラブルを未然に防ぐための最も重要な「予防策」
インプラントを長持ちさせ、トラブルなく快適に使い続けるためには「予防」が何よりも重要です。その鍵は「信頼できる歯科医院選び」と「治療後の徹底したメンテナンス」にあります。
1. 信頼できる歯科医院を選ぶためのチェックポイント
インプラント治療は、どの歯科医師が行っても同じ結果になるわけではありません。以下の点を参考に、安心して任せられる歯科医院を選びましょう。
・CTなど精密検査のための設備が整っているか
・治療のメリットだけでなく、デメリットやリスクも丁寧に説明してくれるか
・歯科医師にインプラント治療の十分な知識と経験があるか
・衛生管理(滅菌など)が徹底されているか
・治療後の保証制度や、定期メンテナンスの体制が整っているか
カウンセリングの際にこれらの点を確認し、ご自身が納得できる医院で治療を受けることが、トラブルを避ける第一歩です。
2. 治療成功の鍵を握る「セルフケア」と「プロケア」
インプラントは人工物なので虫歯にはなりませんが、歯周病と同じ「インプラント周囲炎」にはなります。これを防ぐには、天然歯以上の丁寧なケアが必要です。
・セルフケア(ご自身での手入れ)
歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやタフトブラシ(毛先が一つにまとまったブラシ)を使い、インプラントと歯茎の境目を丁寧に磨きましょう。
・プロケア(歯科医院での定期検診)
セルフケアでは落としきれない汚れを除去し、インプラントの状態、噛み合わせ、ネジの緩みなどをプロの目でチェックしてもらうために、3〜6ヶ月に一度の定期検診は絶対に欠かさないようにしましょう。
これがインプラントを長持ちさせる最も確実な方法です。
まとめ
インプラント治療には、痛みや腫れ、インプラント周囲炎、被せ物の破損など、様々なトラブルの可能性があります。
しかし、それらの多くは原因がはっきりしており、適切な予防策によってそのリスクを大幅に減らすことができます。
トラブルを避けるための最大のポイントは、
・事前の精密検査と十分な説明に基づき、信頼できる歯科医院で治療を受けること
・治療後は、日々のセルフケアと歯科医院での定期メンテナンスを徹底すること
この2つに尽きます。
インプラントは、あなたの人生をより豊かにしてくれる素晴らしい治療法です。
正しい知識を身につけ、信頼できるパートナー(歯科医師)と共に、大切なインプラントを末永く守っていきましょう。
もし何か不安な点や疑問があれば、まずは専門の歯科医師にご相談ください。