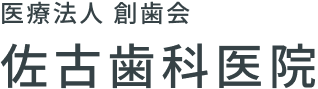2024.05.11
歯周病セルフチェックと自宅ケアの方法|初期症状から予防対策まで徹底解説
はじめに
歯周病は、日本人の約4割が発症していると言われる、国民病とも言える病気です。
歯を失う原因の第1位であり、近年では糖尿病や心筋梗塞などの全身疾患との関連性も指摘されています。
しかし、歯周病は早期発見・早期治療が重要であり、セルフチェックや自宅での対策によって進行を抑制することができます。
本記事では、歯科医師の監修のもと、自宅で簡単に行える歯周病のセルフチェック方法と予防対策を初心者にも分かりやすく解説します。

歯周病とはなにか?
歯周病は、歯を支える組織が炎症を起こし、徐々に破壊されていく病気です。
初期段階では痛みを伴わないため、自覚症状がないことも多く、気が付いた時には重症化していることがあります。
歯周病は、まず歯ぐきが炎症を起こす「歯肉炎」から始まり、進行すると「歯周炎」へと移行します。歯周炎になると歯を支える骨が破壊され、最終的には歯が抜けてしまうこともあります。
また、近年では糖尿病や心血管疾患、誤嚥性肺炎など全身疾患との関係も明らかになっており、口の中だけの問題では済まされません。
歯周病はなぜ起こる?主な原因とリスク要因
歯周病の直接的な原因は、歯の表面に付着する「プラーク(歯垢)」です。
プラークは細菌の塊であり、この細菌が出す毒素によって歯ぐきに炎症が起こります。
プラークは毎日の歯磨きで取り除くことができますが、磨き残しがあると硬くなり「歯石」へと変化します。歯石の表面はザラザラしているため、さらにプラークが付着しやすくなり、歯周病を進行させる悪循環に陥ります。
その他にも、以下のような要因が歯周病のリスクを高めると言われています。
・喫煙
喫煙は血流を悪化させ、歯ぐきの抵抗力を弱めるため、歯周病を進行させる最大の原因の一つです。
・ストレス
ストレスは免疫力を低下させ、歯周病を悪化させる可能性があります。
・不規則な食生活・栄養不足
ビタミンCなどの栄養素が不足すると、歯ぐきの健康が損なわれやすくなります。
・糖尿病
糖尿病は体の抵抗力を弱め、歯周病を悪化させやすいことが知られています。
また、歯周病が糖尿病を悪化させるという相互関係も指摘されています。
・遺伝的要因
歯周病になりやすい体質が遺伝することもあります。
・歯ぎしり・食いしばり
過度な力が歯や歯ぐきにかかることで、歯周組織にダメージを与えることがあります。
不適合な詰め物・被せ物: 段差やすき間があるとプラークが溜まりやすくなります。
これらの原因やリスク要因を理解し、生活習慣を見直すことも歯周病予防には不可欠です。
歯周病の初期症状
これらの症状が見られた場合、歯周病の可能性があります。
・歯茎(歯肉)の赤みや腫れ
・歯磨き時の出血
・口臭の増加
・歯茎の後退
・朝起きたときに口の中がネバネバする
・歯と歯の間に食べ物が詰まりやすい
・歯が浮いたような感じがする
・歯ぐきから膿が出る
これらの症状がある場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。
歯周病セルフチェック方法
歯周病の早期発見・早期治療のためには、定期的な歯科検診を受けることが重要です。しかし、日常生活の中でセルフチェックを行うことで、自身の歯周病リスクを把握することができます。
以下のポイントを鏡の前で確認してみてください。
1. 歯ぐきの色
健康な歯ぐきはピンク色をしていますが、歯周病になると赤く腫れたり、紫色っぽくなったりします。
2. 歯ぐきの形
歯と歯ぐきの間のラインは、三角形をしています。しかし、歯周病になると、歯ぐきのラインが丸く膨らんだり、歯と歯ぐきの間に隙間ができたりします。
3. 歯ぐきの出血
歯磨きをした時に、歯ぐきから血が出ることがあります。これは、歯周病の典型的な症状の一つです。
4. 口臭
歯周病になると、口臭が強くなります。これは、歯周病菌が繁殖することで発生する悪臭ガスが原因です。
5. 歯のグラつき
歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶け、歯がグラグラしたり、抜けたりすることがあります。
6. 朝起きたときの口のネバつき
寝ている間に細菌が増えることで、口がネバつくことがあります。
7. 歯ぐきの退縮
歯ぐきが下がって歯が長く見えるようになってきたら注意が必要です。
セルフチェックの結果、どう判断する?受診の目安は?
セルフチェックで上記の項目に一つでも当てはまるものがあれば、歯周病の可能性があります。
特に以下の場合は、早めに歯科医院を受診することをおすすめします。
・複数の項目に当てはまる場合
当てはまる項目が多いほど、歯周病が進行している可能性が高まります。
出血が頻繁に見られる、または止まりにくい場合: 炎症が強いサインです。
・歯のグラつきを感じる場合
ある程度進行している可能性があります。放置すると歯を失うリスクがあります。
・以前と比べて症状が悪化していると感じる場合
自己判断せずに専門家の診断を受けましょう。
セルフチェックはあくまで目安であり、正確な診断は歯科医師にしかできません。
「まだ大丈夫だろう」と自己判断せず、気になる症状があれば気軽に相談してみましょう。
早期発見・早期治療が、ご自身の歯を守るために最も重要です。
自宅でできる歯周病対策
セルフチェックで歯周病の可能性を感じたら、歯科医院を受診することが大切です。しかし、日常生活の中で以下の対策を行うことで、歯周病の進行を抑制することができます。
1. 毎日の丁寧な歯磨き
歯周病の予防には、毎日の丁寧な歯磨きが最も重要です。歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの間に45度の角度で当て、小刻みに動かしながら、歯垢をしっかりと除去しましょう。
2. フロスや歯間ブラシの使用
歯ブラシでは届きにくい歯と歯の間の汚れは、フロスや歯間ブラシを使って除去しましょう。
3. 定期的な歯科検診
定期的に歯科医院を受診し、歯垢や歯石を除去してもらうことで、歯周病の予防に効果があります。
4. バランスの良い食生活
歯周病は、生活習慣病の一種です。ビタミンCやカルシウムを豊富に含む食事を心がけることで、歯肉の健康を保つことができます。
5. 禁煙
喫煙は歯周病の悪化因子の一つです。禁煙、もしくは減煙を心がけましょう。
6. ストレスの解消
ストレスは、歯周病の悪化原因の一つです。適度な運動や趣味などを通して、ストレスを解消しましょう。
定期的な歯科検診の重要性
歯周病の予防と早期発見には、歯科医院での定期的な検診が欠かせません。
毎日のケアだけでは落としきれない歯石や歯垢を、専門的な器具で除去してもらうことで、歯周病の進行を食い止められます。
3〜6ヶ月に一度の定期検診を習慣にすることで、自分では気づきにくい変化にも早く対応できます。
歯周病の治療方法とは?
もし歯周病と診断された場合、進行度に応じた治療が必要です。
1. 歯のクリーニング(スケーリング)
歯の表面にこびりついた「歯石」や「歯垢(プラーク)」を、専用の器具で丁寧に取り除きます。これは、歯ぐきの炎症を抑える基本の治療です。
2. 歯の根元のクリーニング(ルートプレーニング)
歯ぐきの内側に隠れた歯の根っこの部分に汚れがたまっている場合、それを削り取って表面をなめらかに整えます。細菌が付きにくくなることで、再発の予防にもつながります。
3. 歯ぐきの中まで治す外科的治療(歯周外科手術)
症状が進んでいる場合は、麻酔をして歯ぐきを少し開き、奥深くにある歯石や細菌を直接きれいにする手術を行うこともあります。
4. 治療後のチェックとケア(メインテナンス)
一度治療をしても、歯周病は再発しやすい病気です。再発を防ぐために、定期的に歯科医院でチェックを受けたり、必要に応じてお掃除をしてもらったりします。
まとめ
歯周病は「気づいたときには進行している」ことが多い、非常に静かに進行する病気です。
また、歯周病は糖尿病や心筋梗塞などの全身疾患との関連性も指摘されています。歯周病予防は、全身の健康維持にもつながります。
そのため、日頃のセルフチェックと丁寧なブラッシング、自宅でのケアがとても大切です。
加えて、歯科医院での定期的な検診と専門的なクリーニングによって、歯周病の予防・早期発見・早期治療が可能になります。
歯を失う原因である歯周病を防ぐことは、自分の歯を守ることに直結します。
もし「もしかして?」と思ったら、早めに歯科医院に相談してみてください。
医療法人 創歯会 佐古歯科医院の特徴
▼個別対応
患者さん一人ひとりのニーズに合わせた個別の治療計画を策定いたします。
患者さんとのコミュニケーションを大切にし、それぞれの状態とニーズに応じた治療を提供しています。
▼豊富な知識量
患者さんにインプラント治療のリスクと対策について十分に理解していただくため、分かりやすい説明と情報提供を心がけています。質問や不安がある場合は、専門のスタッフが丁寧に対応します。
佐古歯科医院は、心斎橋駅(北改札)から徒歩1分の歯医者です。
当院では、患者様に最適な治療サービスをご提供出来るように、スタッフ一同お待ちしております。気になる事がございましたら一度ご来院下さい。